社労士はこれから「より深く、より強く」なる。
-50年の歴史とAI時代の展望-

「社労士はいい仕事だよ」
微笑みながらそう語るのは、社会保険労務士法人 大野事務所代表の大野実氏。
社労士という資格ができて丸56年。社会的意義の高い職業であると同時に、私たちは頻繁に行われる法改正やAIの台頭など、さまざまな課題に直面しています。
これからの社労士が誇りを持って前に進むためには、どのような視点を持てばいいのか。そのヒントを求め、HRbase代表の三田が、大野氏にインタビューに伺いました。

社会保険労務士法人 大野事務所
代表社員/特定社会保険労務士
大野 実 氏
神奈川大学法学部を卒業後、1977年に社会保険労務士として独立開業。以来、50年近くにわたり人事・労務管理の第一線で活躍。
その豊富な実務経験と深い知見を活かし、東京都社会保険労務士会会長、さらには業界のトップである全国社会保険労務士会連合会会長(2019年~2025年)という重責を歴任。在任中は、社労士の地位向上と制度の発展に尽力し、業界全体を力強く牽引した。
現在は連合会の顧問として、長年の経験で培った知見を活かし、さらなる社会貢献を続けている。

株式会社HRbase
代表取締役/社会保険労務士
三田 弘道
兵庫県西宮市生まれ。大阪大学大学院在学中に社会保険労務士試験に合格。2015年に株式会社Flucle(現 株式会社HRbase)を起業。300社以上の企業の労務管理支援の中で労務領域の属人化を課題に感じ、HRbaseサービスを開発。
大阪府社会保険労務士会 デジタル化推進特別部会員。ITや業界活性化のテーマで毎月約10本のセミナーに登壇。

プロローグ
三田
2025年10月1日、社会保険労務士法の一部改正が行われました。
大野先生が先頭に立って進められましたが、改正の背景などを教えてください。
大野
今回の社会保険労務士法の一部改正には、社会保険労務士の使命に関する規定の新設と、労務監査に関する業務の明記などが盛り込まれています。中でも「社会保険労務士の使命」に関しては私も思うことが多くあり、起案する立場として力を入れたところでもあります。
【社会保険労務士の一部を改正する法律の概要より一部抜粋】
1 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
社会保険労務士法の目的規定を改め、「社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする」旨の規定を設けたこと。(第1条関係)
三田
先生が「社労士の使命」に対して思い入れを持っていた理由をお聞きできますか?
大野
社会保険労務士法は、もともと労働保険などの手続き業務を円滑に進行させるための制度を確立することを目的として制定された法律で、「この法律は・・・」という書き出しで「・・・を目的とする」という条文が記載されていました。
そこでの社労士は、「社会保険関係の手続き業務を担うための役割」として位置づけされていたわけです。結果として、社会保険の書類作成・手続きは、社労士の独占業務となっています。この社労士でなければできないという「独占業務」が明記されたことで、今日の社労士制度が確立されたと言えます。
私たち社労士は、56年の歴史を踏まえながら社会の大きな変貌に対応してきました。しかしその中で私は、「社労士は、この『事務手続きのための法律』という枠内に留まっていて良いのだろうか?」という課題意識を強く持っていました。
そして私たち自身が、社労士としての使命・理念・こころざしといったものを社労士法の使命規定として掲げることが、これからの社労士にとって何より大切だと考えたのです。
念願であった「第9次社労士法改正」が2025年6月18日に可決・成立したことで、誰もが「社労士になって良かった」と思え、私としても「自信をもって将来を託せる素晴らしい仕事だ」と感じられる制度になったと思っています。
はじまりは飛び込み営業
三田
その課題感は、先生の48年のご経験があってこそ生まれたものかと思います。これまでの社労士の歴史を振り返りながら、大野先生の考え方の背景を教えていただけますか?
大野
私は学生時代に資格を取得し、そのまま社会保険労務士事務所に入所しました。当時は「社労士」という制度自体がまだそこまで認知されていませんでしたが、それでも「専門家」と言うより「実務家」として、手続き業務をまじめに一生懸命、そしてフットワーク軽く行っていれば、ある程度の仕事を得ることができた時代でもありました。
ですから24歳のときに開業した駆け出しであっても、クライアントに対して「急ぎの案件であれば、すぐに走って対応しますよ!」といった具合に迅速に対応していれば何とかなったのですね。

三田
なるほど。社労士は専門家というよりは実務家で、早く正確に事務手続きができることが価値だったのですね。
大野
営業活動としても、企業を一軒一軒、直接ピンポンして回るという時代でした。そもそも「社会保険労務士」という存在自体が認知されていなかったものですから、「保険屋さんですか?」と聞かれることもしばしばありました。
それでも「労働保険や社会保険の手続きは大変でしょう?」と、企業の抱える潜在的なニーズを喚起しては、仕事を受注していきました。
今ほど法改正が頻繁に行われる時代ではありませんでしたが、景気が良かったこともあり、働く人もどんどん増えていました。「毎月様子を伺いに顔を出しますね」「なんでも相談してくださいね」と言って、「御用聞き」のような形で営業をしていたことを今でもよく覚えています。
三田
そうなると、数の勝負ですね。
大野
しかしそのような私たちの体験が、先ほどお話しした課題意識へつながっているのも事実です。たとえば、今でも人数ベースの顧問報酬規定を作成する社労士が多いですよね。私たちの時代のやり方を踏襲してくれているのだと思いますが、私はその考え方自体を変えていかなければいけないと思っています。
なぜならこれからの社会保険労務士は、単に事務手続きを行う「実務家」として留まるのではなく、「より卓越した専門家」へと進化していく必要に迫られているからです。
たとえば50年前に私が勤務した最初の事務所では、小さな商店から月1万円の契約をいただき、1人が40~50件を担当して「こんにちは!」と走り回っていました。
私が算定の時期にクリーニング屋さんに集金に回ったとき、「すみません、今月は算定基礎届を出すので2万円になります」と言うと、「いいねあんたらは」、って言われてしまった。きっと私たちが涼しい部屋でデスクに向かって、パパッと書類を作成しているだけのように見えたんでしょうね(笑)
三田
そう言われてしまうと、こちらも辛いですね(笑)
大野
私も仕事ですが、ワイシャツ1枚いくらの商売をしているおかみさんから2万円を受け取って事務所に帰るのは、つらかった。仕事をして「ありがとう」と言われて報酬をもらいたい。そもそも、適正な報酬とはいくらなのだろう? 社労士のあるべき姿はどこにあるのだろう・・・? ということをずっと考えていました。
だから、これからの社労士が実務家でありながら、さらに専門家として進化していくのなら、自分の仕事の価値や、その1万円の根拠を明確にしないといけないと思うのです。だって、従業員数に応じて、何人だといくらという報酬の決め方は、今では説得力はないでしょう。
もちろんそれは「見せ方」の問題でもあるのですが、もっと根本的な話をすれば、私たち自身が社労士の持つ真の価値をもっと理解することから始めることが大切だと思います。
三田
そう考えると労務監査はシナジーが高いですね。提供できることとアウトプットが明確で、具体的な改善にもつなげられます。
大野
社労士法にも、以前から労務管理の専門家としての「労務監査業務」はありました。しかし時代の要請もあり、「労務監査に関する業務の明記」をすることで社会や社労士自身に対して労務監査が社労士の業務であることを周知・明らかにする意味で、明記したところです。
これから、社労士が行う労務監査の手法や監査の品質を担保する仕組み等を確立していく必要があります。
三田
なるほど!

手続き給与の黄金時代を経て、コロナで業界が一変
三田
今の私たちが、大野先生世代の方々の苦労と実績に支えられていることがよくわかりました。
大野
昔は人口ボーナスの時代で、民間企業も「去年よりも今年、今年よりも来年が好調」という時代でした。手続きをしながら企業の発展に寄り添い、訪問時には「お子さんの誕生おめでとうございます」という会話もできた。
だから保険屋さんに間違えられながらも、若輩者でも経済的な基盤を築けたし、資格を活かして社会活動ができました。
今の社労士と企業との関係性の原点や、社労士に対する信頼と評価は、圧倒的な量の、多様な手続き業務を積み重ねてきたという事実に対する評価の蓄積です。
三田
そのおかげで、相談業務などのいわゆる三号業務が増えても対応できる土壌ができてきたと思うのですが、実務家からより多様性を持った専門家へ進化した明確な時期はあったのでしょうか。
大野
きっかけのひとつはコロナによる社会変化でしょう。お金よりも働きがいという志向や、多様な働き方が生まれ、企業の制度設計ニーズも増大しました。そのあたりから社労に求められる役割も多様化し、「コンサルティング」の看板を掲げる先生も増加したと思います。
三田
確かにコロナ禍で、働き方自体が大きく変わりましたね。その変化の中には、社労士業務でのIT活用も含まれていると思うのですが。
大野
そうですね。IT化の進展は大きな変化です。
たとえば私の若い頃は、算定基礎届の作業は3か月分の給与計算が確定してから電卓で算定し紙ベースに書き込み、年金事務所当に届け出るという流れでした。それがExcelが登場し、さらに専用のシステムが登場し、電子申請で…という具合に進化してきました。
しかしIT化で大量のデータを扱えるようになった反面、セキュリティリスクも格段に上がっています。これまでとは、必要な知識や対応すべきリスクの種類が変わってきていると言えます。
三田
実務家から専門家に進化する過程で、セキュリティなどの新しい知見を身に付ける必要も出てくるのですね。
大野
だからこそ私たちは常に勉強を続け、自分たちの提供する「価値そのものを高める」のと共に「価値の見せ方」についても工夫をしていく必要があります。
そして、何に対する報酬なのかを自分たち自身がしっかりと認識し、その然るべき報酬を受け取りながら、持続可能な事務所を構築していく必要があるのです。
大変な道のりではありますが、これまでの延長線上だけでは未来は描けない。今この変革に着手しなければ生き残れないかもしれない。私はそれくらいの危機感を持っています。
三田
生き残れないかもしれない、というお言葉を大野先生からお聞きするとドキッとします。
大野
デジタル化は世の中にとって間違いなくプラスですが、私たち社会保険労務士も相当に気を引き締めていく必要があります。
昔は目の前で印鑑を押していただくことができて、その場面で、いろいろな相談や会話が生まれました。また、たとえばAさんに渡す書類を誤ってBさん宛ての封筒に入れてしまったとしても、すぐに電話して「今すぐ取りに伺います、申し訳ありません!」で済んでいました。つまりミスも成果も互いに見えやすく、コミュニケーションの中で解決ができていたわけです。
しかし今は状況が一変しました。
オンライン申請やWeb会議も浸透し、依頼先に寄り添う形でのサポートが、激減したように感じます。顧問先からは私たちの業務の動きが見えにくく、その結果「対応が遅いじゃないか」とお叱りを受けることはあっても、面と向かって「ありがとう」と感謝の言葉をいただける場面が、一気に減っています。
これからは、そうしたコミュニケーション戦略まで含めて、新しい価値観へとシフトしていかなければならないということです。
三田
社労士の「やりがい」の話にもつながりますね。社労士試験という難関を越えてきた私たちが、きちんと価値提供をして、感謝も受け取れる世の中にしていきたいと思います。
大野
その通りです。 手続き業務がなくなることはありませんし、今後も手続き業務があることは社会保険労務士の強みであり続けると思います。ただ、その業務の進め方、そして何より顧問先とのコミュニケーションの手法は、確実に変わっていくでしょう。
それは一見大変なことのように思えますが、見方を変えれば非常に楽しみな変化でもありますよね。

時代の立ち上がりに、何を変えればいいのか
三田
大野先生が変化を「楽しみ」と捉えられていることを強く感じます。
ここからは、私たちが変わっていくためのヒントをお聞きしたいと思います。
大野
まず、社労士の強みは、手続きや給与計算に付随するリアルな人事情報を持っていることです。その情報を意思決定にどう活かすか、会社の理念や方向性にどうリンクさせられるかを顧問先に提案することが、労務管理の専門家である社労士の仕事だと思います。
今、企業経営において「人的資本経営」が注目されています。「人」「物」「金」の資本の中で、何よりも「人」を大切にする社会が求められています。
さらに、事業ポートフォリオとともに人材のポートフォリオについての関心が高まっています。
三田
人材のポートフォリオですか。
大野
どのような部門にどれだけのお金を投入し、いくら利益を得るかが「事業ポートフォリオ」、その計画に対してどの事業にどのような人材を採用し、どのように配置し、どのように育成し、どのように処遇していくかといった視点からの取り組みが「人材のポートフォリオ」といわれるものです。
社労士は給与計算や社会保険手続きなどの業務の中で、常にリアルな従業員の情報を得ることになります。
そこで、社労士とペイロール系の会社や人事情報系の会社が協力し、従業員の情報項目の要件定義を共通化することで、リアルな人事統計データを構築しようとする構想を持っています。
もう3年以上検討を進めてつつ、未だに構想の域を脱することができていないのですが、このような構想は夢のような、ワクワクするテーマでもあります。
三田
それは面白いですね。
大野
「人的資本経営」という言葉も市民権を得てきましたが、真正面からこれに向き合える職業は社労士だけだと思っています。なぜなら私たちは、働いている人のリアルな情報、さらには企業のパーパスやリテンション、働く人のエンゲージメントなど、目に見えにくい要素までも総合的に扱う専門家だからです。
昔から、人的資本経営という言葉はなかったけれど、「ヒト、モノ、カネで『ヒト』を扱うのが社労士だよ」という言い方はされていたでしょう?
それが、社会のデジタル化が進み、社労士により多様で高度な専門性が求められるようになり、いよいよ可視化できるようになってきた。
だから、大きく変わるチャンスなんですよ。
「書類の作成・届け出が社労士の報酬の源泉のすべてとし、作成する書類の量」を手がかりとするのではなく、手続きや相談・制度設計そのものの成果に対する価値に対する報酬であり、事務所の持続可能となる適正な報酬を自ら提示するよう、変わらないといけません。
三田
システムで書類を処理できるようになり、書類の枚数=価値ではないということですよね。
大野
そうです。今のデジタル社会においては、100人も1000人も処理の時間があまり変わらないからこそ、専門性が求められるし、AIやセキュリティの知識アップデートも避けては通れない。さらに、当然ながら、そういったインフラの整備にはコストがかかりますし、優秀で高い専門性を持ったメンバーを事務所に迎えたいと思えば、それに見合うだけの体制もととのえる必要がありますよね。
大変だと思いますが、時代の立ち上がりとはそういうものではないでしょうか。
三田
これまで何度も時代の変わり目を見てこられた大野先生の言葉は、とてもリアルで、身も引き締まります。
大野
私を含め、今社労士業界を牽引する人たちは、昭和のイケイケ時代に先頭切って走ってきた人たち。時代をつくってきた自負はありますが、私たちの価値観は、大きく変貌する社会にもうついていけないのかもしれません。変われないということかもしれません。
「生産性を高める」と口で言うのは簡単ですが、絶対的な方法はありません。だからこれまではシステムや属人的なパフォーマンスに依存していました。
しかしAIの出現で状況は一変しました。これは年齢や経歴を問わず、全員が一斉に「よーいドン」とスタートを切れるタイミングが到来したことを意味しています。
AIは、もともと優れた人がさらに優れるためのツールではありません。そうではなく、ごく普通の人が一気にピカピカに輝けるようになるためのツールです。だからこそ、私は繰り返し「今、変わらないともう間に合わない!」と皆さんに伝え続けているのです。
目指す方向性を決めるために
三田
変化の重要性についてよく理解できました。しかし選択肢が多い時代で、業界や自分がどの方向に進化していくべきか・・・迷っている方も多いと思います。
大野
確かに社労士の業務領域は驚くほど広がりが深まっており、「これがサービスメニューです」と羅列したら顧問先が増える時代ではないですよね。
でもその課題は、今の時代を生きる皆で考えたらいいと思いますよ。業界全体でも、タレント性や発信力がある人がどんどん牽引すべきです。どこかで誰かが突き抜けないと、社労士業界は社会の変化スピードについて行けません。
今、必要とされる経営の視点で言うと「アジャイル思考」ということかもしれません。
三田
足並みを揃えることで発展してきた業界ですが、いよいよ次のフェーズに入ったということでしょうか。
大野
そうですね。だから現状把握のために社労士実態調査なども実施したわけです。数字がリアルすぎて賛否もありましたが、社労士の実態を明らかにし状況を確認するとともに、一方では、危機感も持っていただければと思います。
さらに、その後開業会員を対象にした「パネル調査」で、事業タイプを3つに分類した追跡調査も実施したところです。
この調査で改めて「社労士になって良かった」、「社労士という仕事が、将来を託するに足りる素晴らしい資格である」と自信と勇気が持て、それを実感できる結果だったと自負しています。いま一度、「社労士実態調査」「社労士パネル調査」をご覧いただければ幸いです。
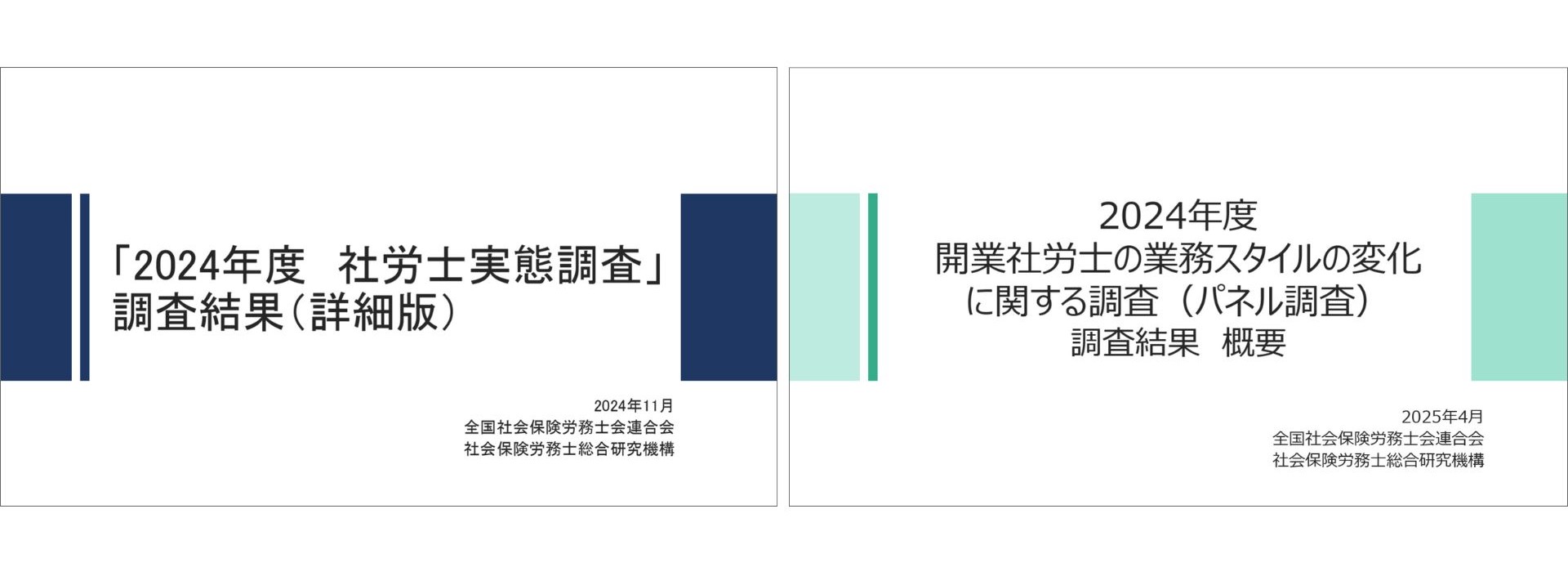
三田
自分がどこを目指すかによって、変化の方向性も変わりますね。
大野
社会保険労務士法の中に「労務管理」という言葉が初めて入ったのは、確か第四次法改正だったと記憶しています。
それまでは「労働及び社会保険の専門家として、それに関する相談に応じる」という表現に留まっていたものが、この改正で初めて「労務管理」という言葉で包括的に定義されたのです。
ただ、その頃はまだ景気のよい時代でしたから、事務所の体制まで変えなくても結果は出ていました。そのため「労務管理」という言葉が条文に明記されたことに対する変化のニーズはそれほど強くなかったと感じています。
しかしバブル崩壊があり、さらにコロナ禍を経て、世の中はどんどん変わりました。こんなにも「ひとを大切にする社会の実現」が叫ばれる時代になるとは誰も思わなかったでしょう。
それでも、社労士の知名度は十分でないと言われながらも国家資格で、社労士登録者は46000人います。弁護士とほぼ同じぐらいの規模・組織で50年以上の歴史があるわけです。これまで社会の中で積み上げてきた信頼関係をベースにして、自信を持って看板を出し、自分の感性に合う仕組みをつくっていけば大丈夫ではないでしょうか。
考え過ぎず、柔軟な行動を
三田
先人が築き上げてきた信頼の看板を、一層磨いていくのが私たちの使命ですね。
大野
昔はダイレクトメールを1,000件送ったり、叱られながら事務所案内のポスティングをしたりしないと、なかなか顧問先を見つけることはできませんでした。
しかし、今は情報発信が非常に容易になりました。自分の強みを打ち出せば出すほど、それが直接仕事へとつながる時代になったではありませんか。
私も相当ガンガン営業をやりましたけど、それでも50年かかってしまった。それを2~3年で追い越してもらえる時代ですよ。若い方に発破を掛けたくなる気持ち、理解していただけますか(笑)
三田
はい。このようなテーマのインタビューでは、「スキルを磨く」のようなお話になりがちですが、社労士と自分の価値を俯瞰し、柔軟に行動に移されている先生の姿勢に刺激を受けております。
大野
今は悶々とした世の中で、政治も経済も社会も大きく揺らいでいて、先が見通せない時代だと思います。だからこそ「AIに仕事が奪われてしまう」といった不安が叫ばれているのでしょう?
でも、こういう時代だからこそ、社労士が活躍できるのも事実です。
「何をしているかわからない」といわれようとも、資格に守られながら、不安の多い社会体制に対して専門的なアプローチができるのが社労士ですよ。
スーパーマンではない私でも、こんなに充実した仕事人生を送れた。だから柔軟に、時代の潮流に乗っていけば、必ずうまくいきます。
三田
そのメッセージは、どのような社労士先生に届けたいですか?
大野
若手世代に限らず、すべての社労士先生ですね。
経験を積んできたという自負や自信は大切ですが、経験が長くなればなるほど柔軟性は失われます。顧問先との信頼関係という財産も、私たち自身が変化しなければ維持できなくなる可能性もあります。
三田
変わることを怖がっていては、現状維持もできなくなるということですね。
大野
私自身もいろいろ考えてきましたが、未来は誰にもわかりません。
わからない中にあっても、自分なりに起こりうる未来から逆算して現在を描き、立ち止まることなく動きながら考える「アジャイル思考」が大切だと思います。
社労士としての目的地へ、皆で前進するためのエール
三田
最後になりますが、先生が職業として選択し、約50年にわたって取り組まれてきた「社労士という仕事」のやりがいについてお聞かせください。
大野
それはもう、お客さんから「ありがとう」と言っていただくこと。
それに尽きます。
ありがとうって、元気になる言葉なんですよね。
私は「ありがとう」という言葉をいただくたびに、社労士という仕事を通じて「自分が生かされている」ことを実感し、元気になれる毎日を送っています。
私たちは、この感謝の言葉を顧問先と交換し実感するために、専門性やスキルを磨き続けます。相手に寄り添い、「この課題をどう解決していこうか」と共に悩み、考えることこそが仕事になる社労士は、本当にこれ以上ないほど良い仕事ですよ。
三田
その気持ちを忘れなければ、AIに仕事を奪われることなどありませんね。
大野
そうですね。
AIに仕事を奪われることは、絶対にないと宣言しておきましょう!!

社労士という仕事にこだわりをもって、社労士という仕事を貫き通すことが、すべてだと思います。
私はコロナ禍が始まった時期に会長になりました。確かに大変ではありましたが、今だからこそ社労士という仕事はやりがいのある仕事ですし、そして社会も、社労士の専門性を強く求めていると感じています。
社労士という仕事の領域は、とても多様化していて、自分自身のライフスタイルにあわせていろいろ描ける資格だと思います。
ぜひ「自分がどのような社労士になりたいか」を見つめ、自分らしい社労士像を描き、その社労士像にこだわり続け、貫いてみてください。
このたびの使命規定の新設も、
社労士としての「使命」、命がけで貫くこと・・・、そして社労士としての存在意義、決意、理念、責任・・・といった想いを社会に宣言するものでありました。
社労士を取り巻く社会環境は、高齢化と人口オーナス、資本主義の劣化、そして何よりもデジタル社会の到来というとても大きな変化を迎えています。
AIやテクノロジーを味方につけ、誇りを持てる「社労士という仕事」を通じて、皆でともに前進して行こうではありませんか。
貴重なエピソードとエールをありがとうございました。
社労士が時代にあった活躍をし、顧問先、ひいては社会全体にその価値が行き渡るよう私たちも願っております。
Our Voices
「だから、この仕事は面白い。」
全国各地、様々なフィールドで活躍する先生方のリアルな声。日々のやりがい、そして未来への展望について語っていただきました。

